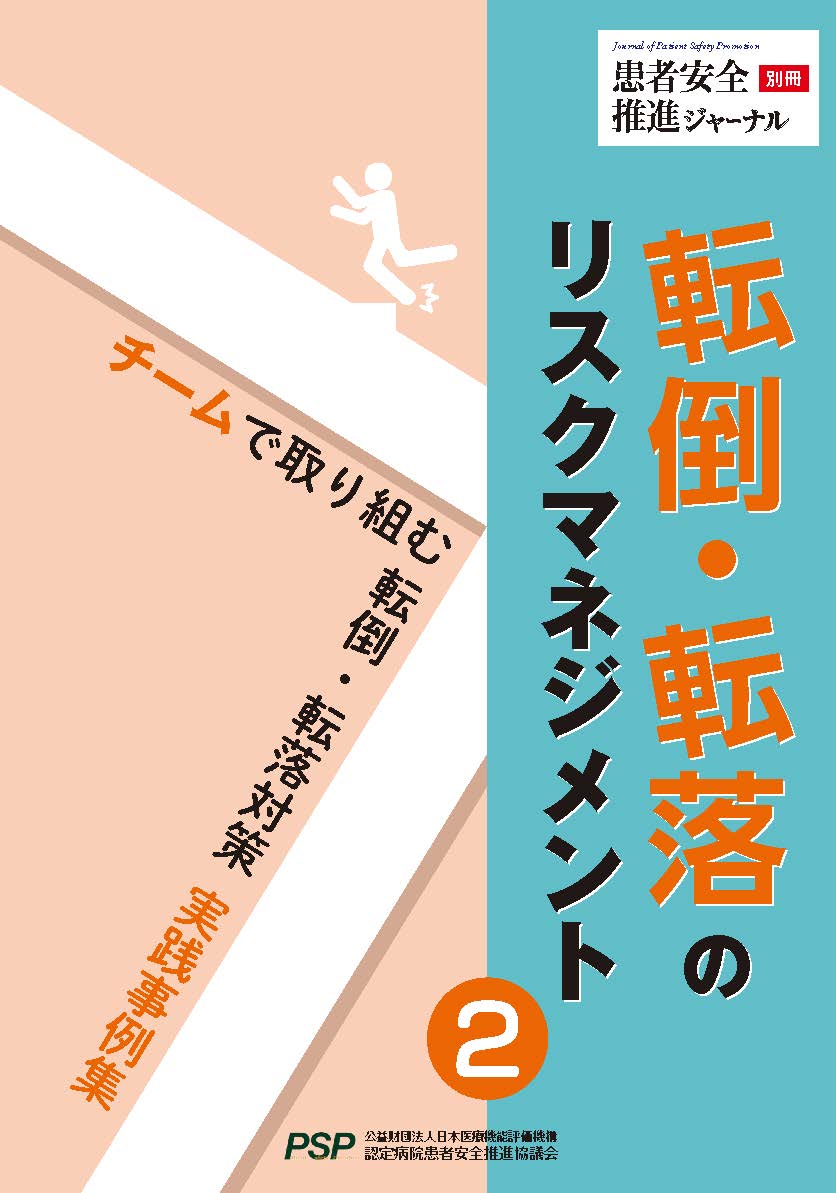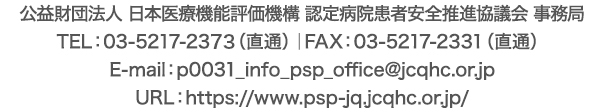【掲載日】2024年11月20日(水)
[別冊]転倒・転落のリスクマネジメント 2 を発行しました
| 【発行日】 | 2024年11月発行 |
[別冊]転倒・転落のリスクマネジメント 2
認定病院患者安全推進協議会では、年4回の「患者安全推進ジャーナル」のほかに、年1回程度、テーマを選んで「別冊」を発行しています。今回、そのテーマとして2016年に続いて、「転倒・転落」を取り上げることにしました。
2016年の別冊では、全体の構成を考えていくつかのテーマを設定し、テーマごとに施設での取り組みを取り上げました。今回はテーマを決めずに、特徴的な活動をしている施設に原稿をお願いし、それぞれの主な取り組みを記載してもらっています。特定機能病院から回復期リハビリテーション病棟まで、さまざまな施設からの報告となり、多くの特色のある取り組みがまとめられていて、読み応えのあるものとなっています。
転倒・転落は、患者安全において、以前から重要なテーマですが、近年、その考え方は変化しつつあります。以前は、転ばないことを最優先とし、そのため患者の行動を制限するのもやむを得ないとしていました。しかし、それでは、患者は適切に行動することが困難となり、結果としてますます転倒しやすくなります。倫理的にも、正しい方向とはいえません。まして、転倒・転落をゼロにすることは現実的ではありません。
このようななか、転倒・転落しても、骨折などの重篤な障害をきたさないことを最優先とし、ある程度までは転倒・転落を許容する方向へ、変化しつつあります。例えば、Joint Commission Internationa(l JCI)において転倒・転落は、6つある国際患者安全目標(IPSG)の1つとして重要視されていますが、2024年に発表された第8版の規定では、骨折などの重篤な障害を伴った場合は警鐘事例として重要視するものの、それ以外の転倒・転落はIPSGからは外れ、重要度で扱いが異なっています。
日本全体では年間約9500人(65歳以上、令和3年「人口動態調査」より)が、転倒・転落のため死亡しており、転倒・転落対策は病院に限った話ではありません。転倒は自宅でも起こり、その場合は当然、自身の責任となるのに、病院で転倒した場合に病院が責任を問われるのは理不尽ではないか、という意見は、一見もっともであるようにみえます。しかし、だからといって病院が何もしなくてもいいわけではありません。病院の法的な責任については本別冊の守備範囲を超えるため、ここでは述べませんが、転倒・転落対策を実施するのは、倫理的にも、医療者としても、当然のことといえます。
時代とともに、考え方、患者の特徴、施設の果たす役割は変化し、転倒・転落への取り組み方法も、それに合わせて変化していくものであって、正解はありません。本別冊は、今の時代の、さまざまな日本の施設における特徴的な取り組みの記録です。それぞれの施設が、自施設にあった取り組みを実施すればよいのです。この冊子が、皆さんの施設での新たな取り組みの契機になれば幸いです。
最後に、快く原稿を引き受けていただいたすべての執筆者の方々に、感謝申し上げます。
患者安全推進ジャーナル企画部会 部会長
倉敷中央病院 副院長/臨床検査・感染症科/HQM推進センター/GRM
橋本 徹
購入申込
・会員病院の方はこちら
・非会員病院の方はこちら
内容紹介
・目次
・新刊案内
・読者アンケート
読者アンケートの回答は締め切りました。ご意見・ご感想などがございましたら、お問い合わせよりお寄せください。
ご案内
本コンテンツは会員限定コンテンツです。
協議会に入会をご希望の方はこちら