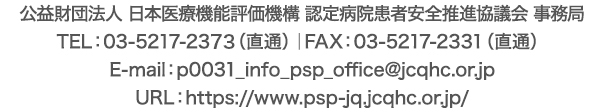【掲載日】2020年12月04日(金)
事例番号 747
物的環境に関連する事例集
病室
ベッド、機器
有
転倒
B. 物の性能のリスク C. 不適切な環境設定・維持管理不足によるリスク D. スタッフによる物の不適切な使用・利用・選択・設置・確認不足によるリスク E. スタッフが作業する上での環境上のリスク
ナースコールの管理不備、機能に関する知識不足による、ナースコールが鳴り止まない環境に対して、対応が適切に行えなかったことによる転倒
・ナースコールが鳴っていてもコールを消すのみで対応していない。
・音の区別ができていないため、ナースコールが多いと誰にナースコールが鳴っているのか把握できずに対応している。
・ナースコールの子機の修理に4台提出し、さらに稼働していたのが2台のみであった。ナースコールの設定で、子機が日勤モードと夜勤モードに分かれていて、親機の設定が日勤モードであり、夜勤モードに設定されていた子機は音が鳴らない状況になっていた。いつの間にか切り替わっていた。頻回にナースコールを鳴るが、使用できるナースコールは親機1台と子機は2台のため、速やかなナースコール対応ができていない。転倒リスクのある患者であり、ベッドサイドにサイドコールを設置し、早期に患者の離床行動を把握するようになっていたが、患者がベッドから離れると一度消したナースコールは鳴らないため患者の離床に対応できなかった。患者は認知症があり離床時は介助を要するが、ナースコールは押せず、支えがあれば、伝え歩きはできるためベッド周囲は歩行が可能であった。
センサーによるナースコールの音を通常の音と区別した。(全病棟統一した) ナースコールの日勤夜勤の切り替え機能は使用せず日勤モードのみにする。ナースコールの子機の修理に速やかに出す。(代替器の準備をする)ナースコールの子機の活用方法。(充電のタイミングを検討する)離床センサーの無駄鳴り防止の工夫をする。(介助中に介助者がコールマットを踏んで鳴らすなど)患者の動きに応じた離床センサーを使用する。ナースコールよりも先取りした援助を行うよう計画する。
患者のベッドと洗面所の配置 ベッドの左側から昇降していた
患者のベッドの隣にあった洗面所 この前で転倒していた
病院で使用している離床センサー3種
今回ベッドサイドのマットのみ使用していた